90歳女性が警視庁を名乗る男女からの電話にだまされ、約150万円を取られる詐欺被害が発生。自宅に「電気協会」を名乗る自動音声ガイダンスからの電話があり、その後警察官を名乗る男からの電話で家が名義で契約されており、暴力団が使用していると告げられ、通帳やキャッシュカードを自宅の郵便受けに置いたところ持ち去られ、約150万円が引き出された。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c20e370f9930880d8fc87263072f2ed4c405ae9
この事象は「特殊詐欺」に該当します。理由は、対象文章が特定の人物(警察官)を名乗る詐欺者による詐欺行為に焦点を当てており、これは特殊詐欺の一例です。電話で信頼性のある組織や権威を装い、被害者のお金や情報を騙し取る行為が行われています。
可視化思考の活用
特殊詐欺のケースでは、被害者の年齢や詐欺手口、被害額などの情報をグラフやチャートで可視化することで、被害の全体像やパターンが明確になります。これにより、警察や関係者は効果的な対策を講じることができます。
- ネットワーク図: 詐欺のケースでは、被害者、詐欺者、詐欺手法、情報の流れなどをネットワーク図で表現することで、関係性や連携の仕方が視覚的に理解されます。これにより、詐欺の仕組みを洞察し、対策を練る際に有効です。
- タイムライン: 詐欺の過程や関連する出来事を時系列に沿ってタイムラインで表現することで、どのような手順で被害が進行したかがわかります。詐欺者の行動を追跡し、対策の着想や法的措置に役立ちます。
特殊詐欺のケースでは、これらの可視化思考が被害の全体像を理解し、対策を立てる上で不可欠です。被害者の情報や行動をグラフや図として可視化することで、警察や関係者は迅速かつ的確に対処策を講じることができます。
教訓
- 疑念を持つことの重要性: 信頼できるように見せかけても、電話での情報提供に疑念を持つことが大切です。状況を冷静に判断しましょう。
- 個人情報の保護: 機関名や個人情報を提供する際は慎重に。詐欺者はこれを利用して信頼を勝ち取ります。
- 緊急を装う手法への警戒: 緊急性を装って行動を急かす詐欺があるため、冷静に行動しましょう。
- 警察や公的機関との確認: 不審な電話があった場合、直接警察署や公的機関に確認する習慣を持ちましょう。
- 偏見バイアス:警察官を名乗る詐欺者が暴力団と関連づけて、被害者に誤った情報を提供することで、被害者に偏見や誤った認識を植え付けることを通じて詐欺行為を行っています。
![SOLPA [Solution Park]](http://solpa.kasouken.net/wp/wp-content/uploads/2025/07/SOLPA_3.png)

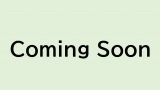
コメント