高松市は高齢者介護者に介護見舞金を支給しており、28人に誤って支給されたことが判明。支給総額は54万円。要介護者が死亡しているにもかかわらず支給が続いており、市は誤支給の返還を求めている。要介護者の死亡確認が怠られたり、データが正しく反映されなかったりしたことが原因。市は再発防止に努める意向。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c20e370f9930880d8fc87263072f2ed4c405ae9
この事象は対象文章は「誤判断」に該当します。このニュース記事では、市が介護見舞金を要介護者が死亡した後も支給してしまったという誤った判断が発生したことが述べられています。要介護者の死亡確認の手続きやデータ管理において誤った判断がなされた結果、誤支給が続いてしまったのです。
可視化思考の活用
高松市の介護見舞金支給の誤判断事例では、要介護者の死亡確認やデータ管理の誤りが重なり、誤支給が発生しました。ここで可視化思考が重要な役割を果たす理由は、次の通りです。可視化を用いることで、要介護者の死亡や支給データの誤りといった複雑な情報を一目で理解することが可能です。グラフや図表を通じて、支給のタイミングや誤りがどのように連動していたのかを視覚的に理解できます。可視化を通じて、要介護者の死亡確認が適切に行われていないことやデータ管理の不備が浮き彫りになります。これにより、問題の根本原因を明らかにし、再発防止策を検討する際の指針となります。
- タイムライン・時系列の可視化: 複雑な出来事の流れや時間の経過をグラフやチャートで表現することで、要因と結果の関係性を理解しやすくなります。例えば、介護見舞金支給の誤りがどのタイミングで始まり、どのように広がっていったかを時系列で表示することで、誤判断の原因特定に役立ちます。
- データの比較と相関関係の可視化: 異なる要素や変数の関係性を図やグラフで示すことで、相互の影響や傾向を把握できます。介護見舞金支給においては、要介護者の死亡確認と支給データの関連性を可視化することで、誤支給のパターンや共通の要因を特定する助けとなります。
以上のように、可視化思考は複雑な情報の理解や問題解決に不可欠であり、特にタイムラインとデータ比較の可視化が重要です。
教訓
- 確実な確認手続きの重要性: 要介護者の死亡確認手続きを怠ることは、誤った支給などの問題を引き起こす可能性があります。確実な手続きの必要性を認識し、実施することが大切です。
- データの正確性と管理: 誤ったデータがシステムに反映されてしまったことが問題の一因となりました。正確なデータ入力と管理は誤判断を防ぐために不可欠です。
- 過度な自動化への警鐘: システムの自動化が進む中で、人間の確認や判断が軽視されることがあります。要介護者の死亡確認など、重要な手続きは適切なバランスを保ちつつ自動化を進める必要があります。
- 透明性と責任の明確化: 誤支給が発覚した際に、市が誤った判断をした人に対して返還を求める姿勢を示したことが重要です。透明性を保ち、責任を明確にすることで信頼性を確保できます。
- 現状維持バイアス:市が要介護者の死亡確認体制を適切に保っていなかったため、本来誤支給すべきではなかった支給を続けてしまったことが示されています。この事例は、既存のプロセスや状況を維持しようとするバイアスが働いていた結果、問題が発生したと考えられます。
![SOLPA [Solution Park]](http://solpa.kasouken.net/wp/wp-content/uploads/2025/07/SOLPA_3.png)

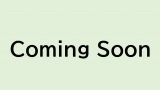
コメント