良い会社に入るためには、一生懸命に勉強して高学歴を得ることが一般的な認識だろう。それは企業が新卒採用をする際の第一段階で、学歴を重要視するからだ。幾つもの段階を経て採用にこぎ着け、基礎教育やOJT(On the Job Training)の後は個々の実力が試される。
ところが期待した成果を出せない人がいる。しかも高学歴にも関わらずだ。なぜだろう。
なぜならば学歴と仕事は一致しないからだ。
「勉強ができる人」と「仕事ができる人」の違いとは
「勉強ができる人」とは、誤解を恐れずに言えば暗記する能力が高い人と言える。授業で学んだ情報を大量に蓄積し、試験問題を一定時間内に解けるかを点数で評価するものだからだ。成績が高得点な人ほど「勉強ができる人」と一般的に言われる。
一方、「仕事ができる人」とは依頼や指示に対して、一定時間内に高品質な結果を出せる人を言う。暗記力は必要とせず、如何に効率的に問題解決ができるか求められるのだ。
「勉強ができる人」≠「仕事ができる人」なのだ。
それにも関わらず未だに企業が採用時に重要視する基準の一つに学歴がある。「勉強ができる人」が採用されるが、仕事ができない人がいるのはここに問題がある。
仕事の答えは一つではない
仕事の答えは一つではない。100%完璧と言う答えは存在しないため、状況にもよるが落としどころに着地しなければならない。試験問題のような解ではなく、複数の解から取捨選択することになる。
完璧主義の人は解の導き出しに時間がかかり、成果に結びつかないケースがあるのだ。
学歴は不要だが学びは必要
「仕事ができる人」になるには、基本的な知識や能力は必要だ。それらを習得するには、学びに加えて実践しなければならない。書籍を大量に購入して読み込んでも、記載された内容を実践しなければ意味がないのだ。
仕事が忙しくなると学生時代のようにまとまった時間が取れなくなる。必然的に学びの時間が取りにくくなるため、隙間時間を上手く作れる能力が必要だ。単純に手の動きを早くすることではない。
自分自身の時間管理について、現状把握した後にあるべき姿とのギャップを見極め、ギャップを改善する「問題解決」能力を高めると必然的に隙間時間を作れるのだ。
![SOLPA [Solution Park]](http://solpa.kasouken.net/wp/wp-content/uploads/2025/07/SOLPA_3.png)

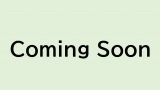
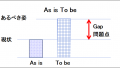
コメント