マルウェア感染のプロセスを知る
マルウェア感染のトリガー(きっかけ)は、多種多様かつ巧妙に変化している。例えば、メールを送り偽サイトへ誘導するフィッシング詐欺や、有名企業やサービスのURL(ホームページの住所など)に似せて本物と錯覚させるタイポスクワッティングが有名だ。これらは単なる手口に留まらず、心理面を巧みに突いてくるのだ。
マルウェア侵入の罠に気づき回避する意識を持つ
罠に気づき回避する意識を持つ
攻撃者は巧妙な罠を仕掛けて騙される人を待っています。錯覚や勘違いが原因で、罠と見抜けない人が多数います。
「マルウェアに感染」と偽メッセージを表示(罠)し、ボタン(罠)を押させる
○○が貰えるキャンペーン(罠)に応募するため、特設サイト(罠)へ移動させる
役所をかたり(罠)還付金の支払い(罠)と称して、ネット銀行用のアプリ(罠)をインストールさせる
偽のフリーWi-Fiを設置(罠)し、利用させることでマルウェアを侵入させる
罠の事例をご覧になり、「マルウェアの知識と関係ないもの」と気づいたと思います。ここに挙げた罠は氷山の一角に過ぎず、巧妙化したものや新たな罠が次々と発見されています。これらの罠に騙されないためには、様々な罠の存在を知っておくことが大切です。
つまり、現状の罠を知ることに加え、新たに発見される罠も定期的に知ることです。
主な手法
フィッシング
フィッシングとはインターネットを利用して、予め用意した偽サイトへ誘導させる手口です。プレゼントなどお得な情報を見た人が、偽サイトへのリンクをクリックします。偽サイトでは応募のための個人情報を入力させたり、更にお得な情報へと誘導させるなど巧妙な手口があります。
プレゼントだけでなく、銀行口座から不正な引き落としが あった、契約更新が迫っているなど様々な方法で、偽サイトへ誘導させます。
- 「アカウントが不正利用」などメールを受け、リンク先へ飛ぶとアカウント情報を入力させる
- 「高額くじに当選しました」とメールを受け、リンク先へ飛ぶと個人情報を入力させる
- 「新作ゲームが無料」とSNSの投稿を見て、リンク先へ飛ぶとアプリをインストールさせる
- Web閲覧中に「アダルトサイトの契約完了」と表示が出て、リンク先へ飛ぶと利用料を請求される
- 他多数
端末の脆弱性を意識し対策を講じる必要がある
「端末の脆弱性(ぜいじゃくせい)」とは、プログラムの不具合を指します。端末には複数メーカーのソフトウェアがインストールされており、様々な不具合が起きる可能性があります。
WindowsやAndroidなど基本ソフト(OS)のセキュリティホールを狙う
各種アプリのセキュリティホールを狙う
プリンタやデジカメなどを接続するソフトウェア(デバイスドライバと呼ぶ)のセキュリティホールを狙う
セキュリティ対策ソフトのパターンファイル未更新
パソコンやスマートフォンを使う場合、基本的な知識を身につける必要があります。特にセキュリティに関する知識は必須で、対策を怠ると自分自身が被害者にあううえ、友人・知人にも迷惑をかける可能性があります。具体策として次の方法があります。
![SOLPA [Solution Park]](http://solpa.kasouken.net/wp/wp-content/uploads/2025/07/SOLPA_3.png)

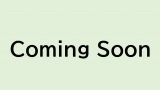

コメント